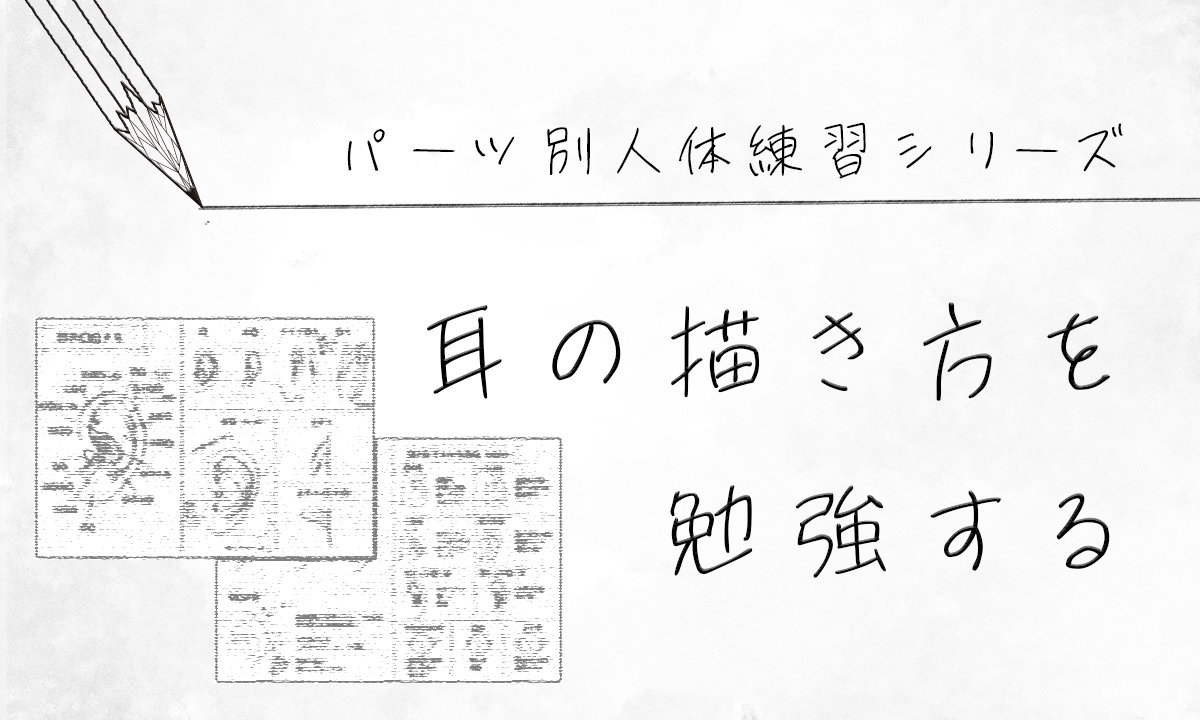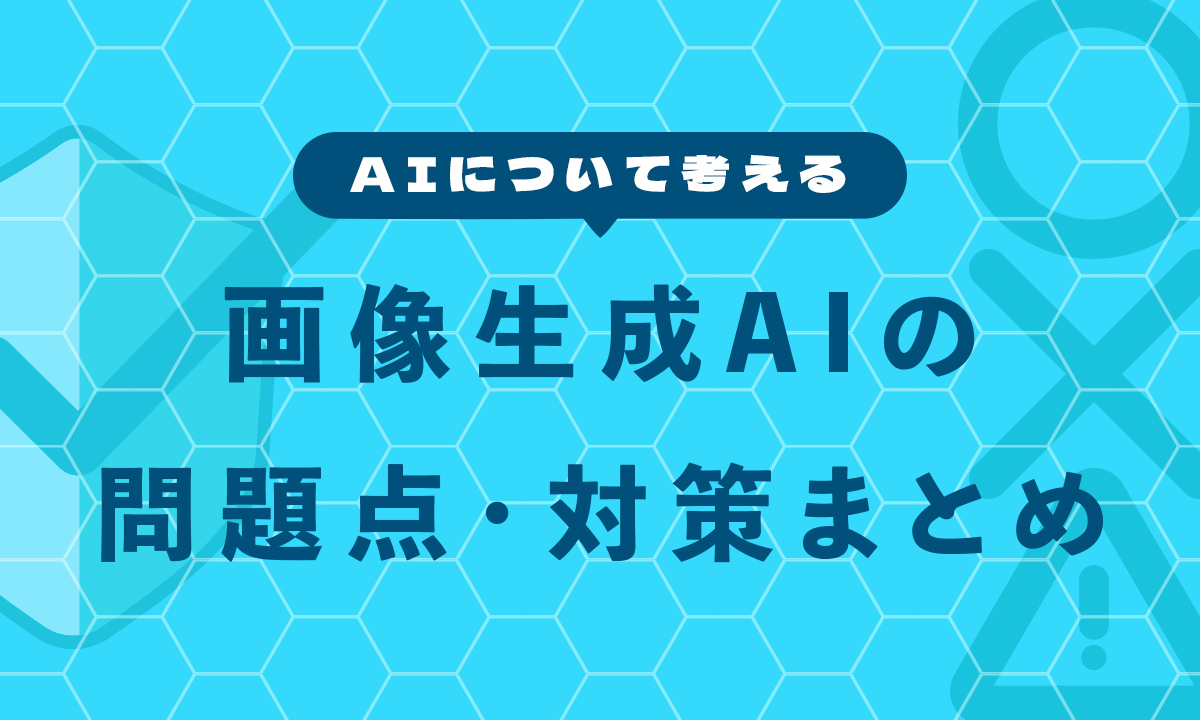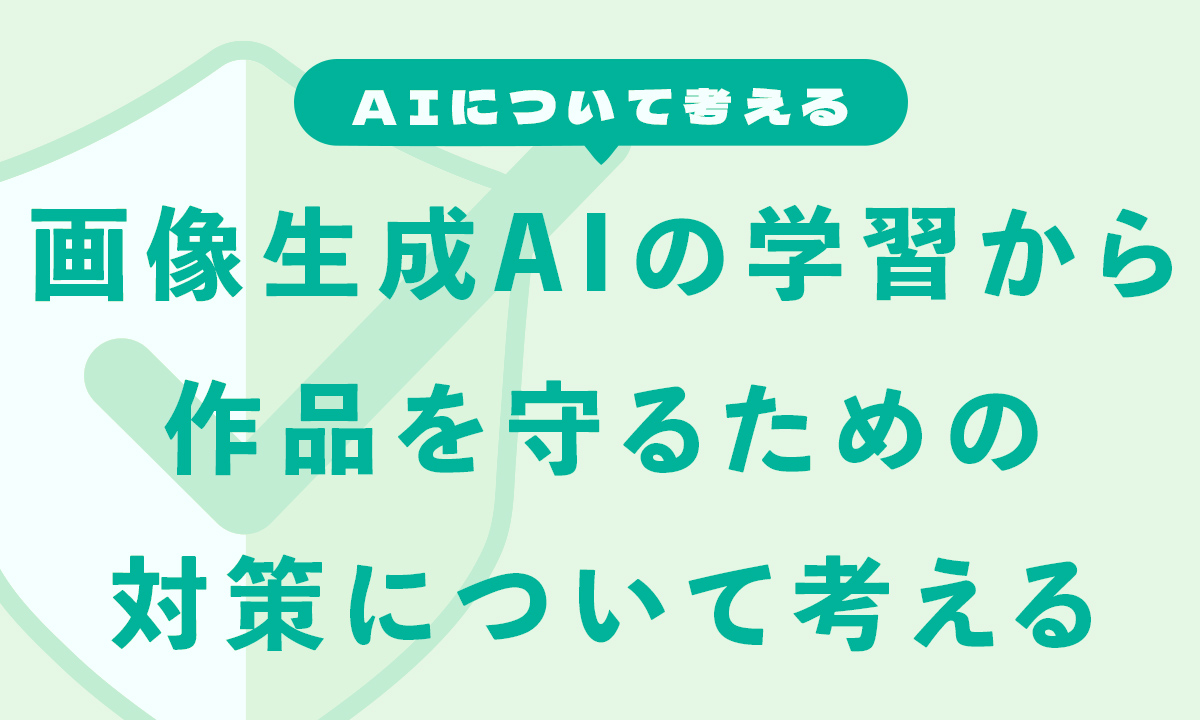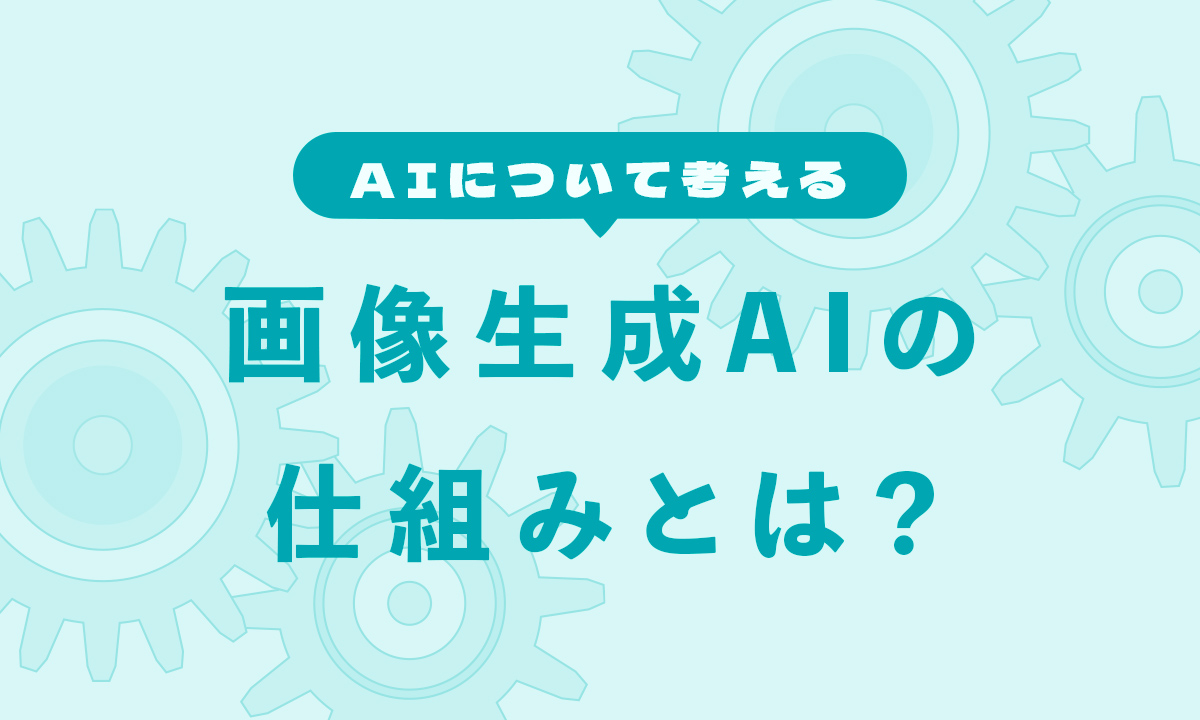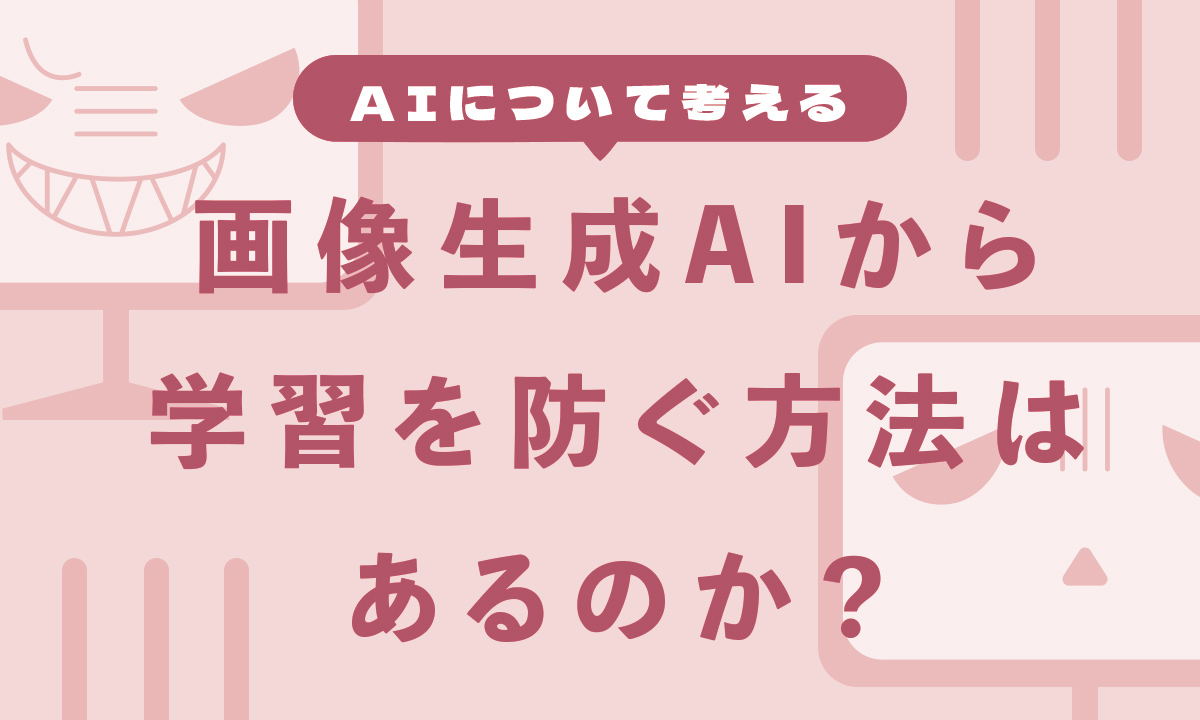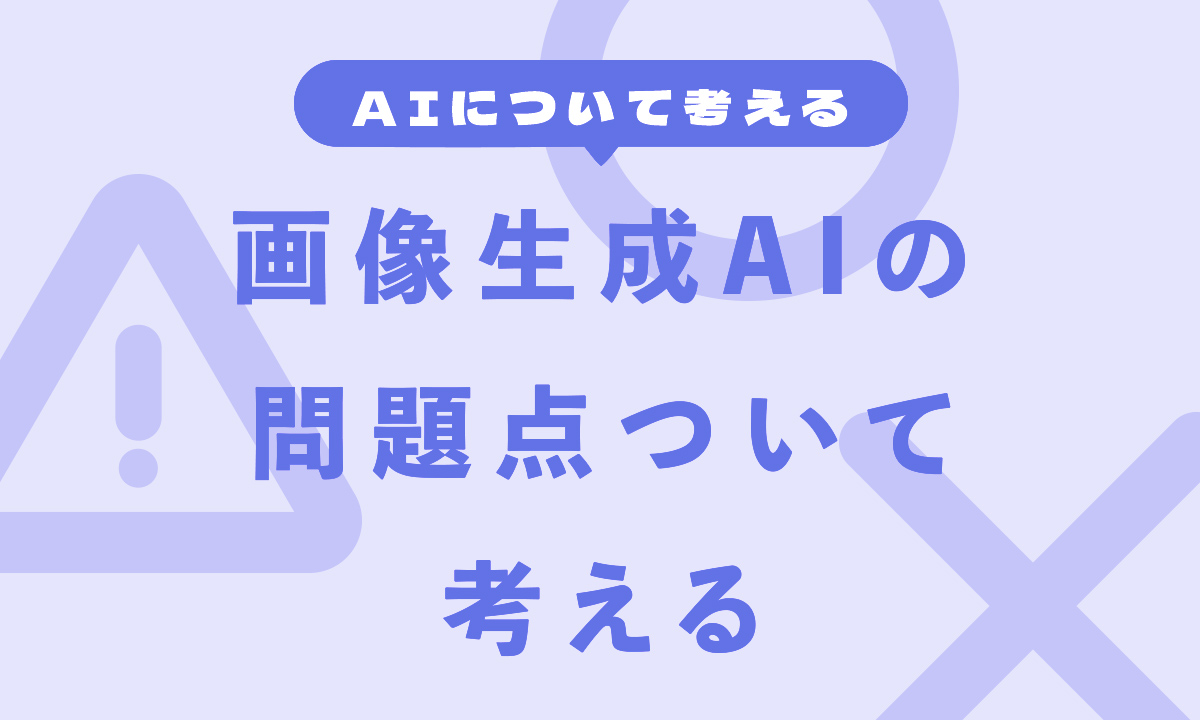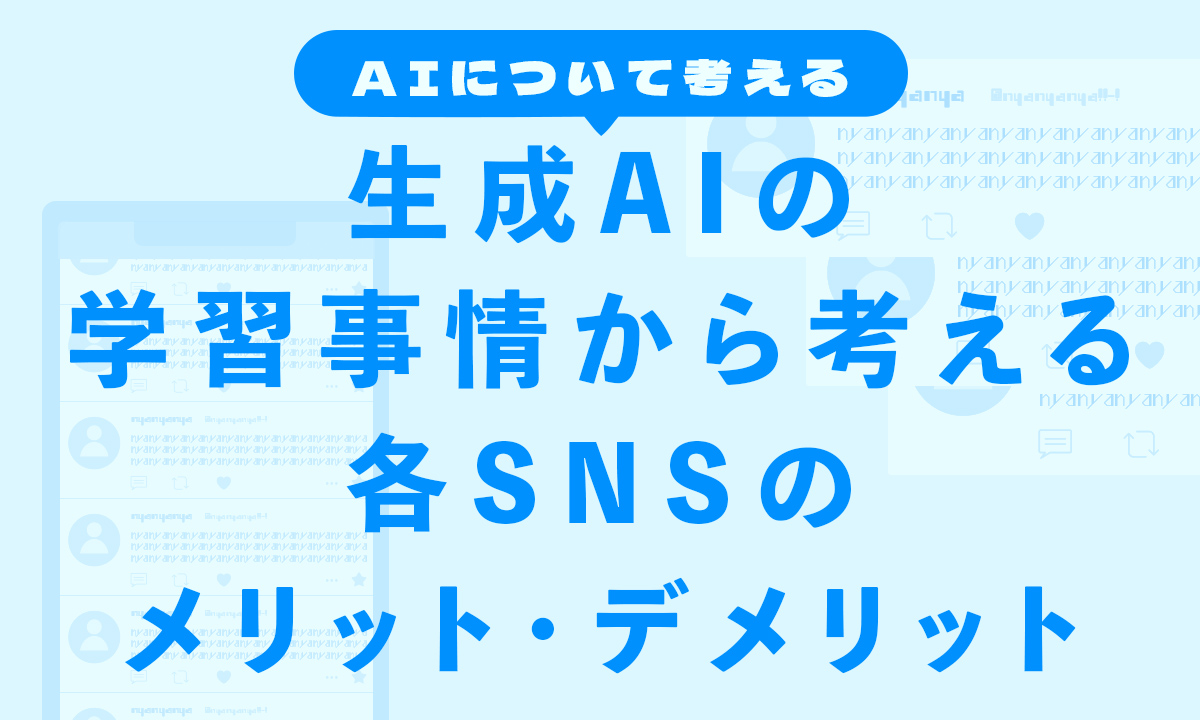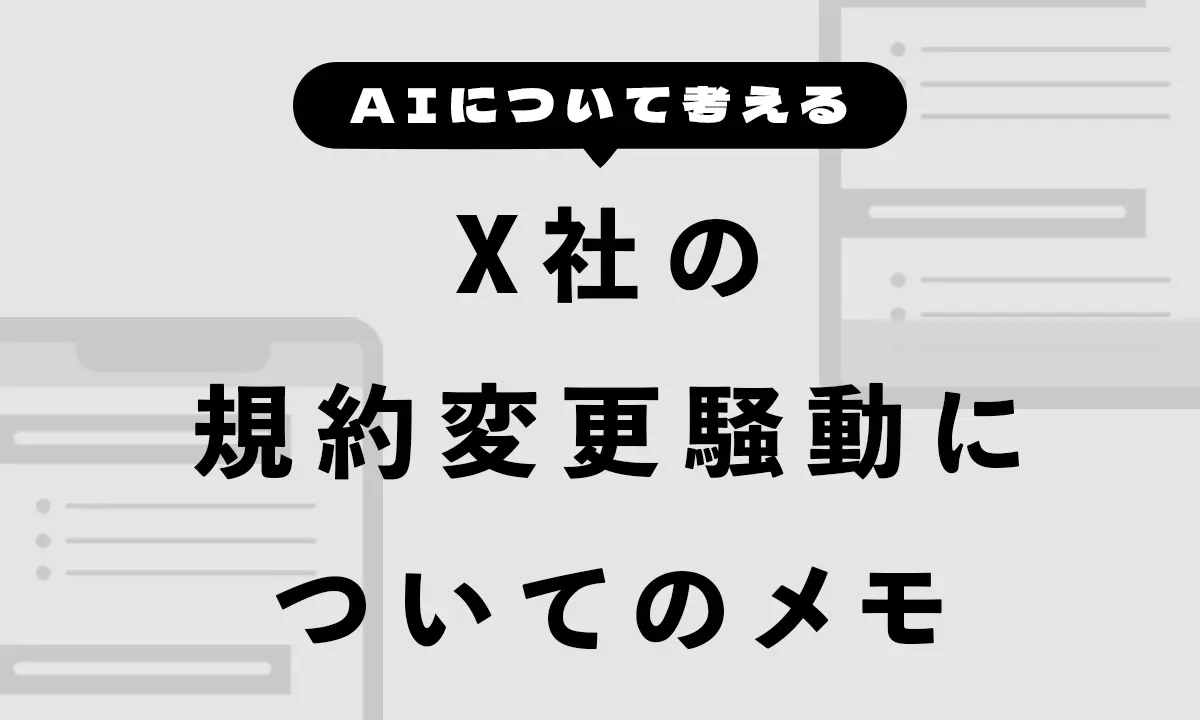この記事にはプロモーションが含まれています。
本の感想日記①いつも「時間がない」あなたに: 欠乏の行動経済学
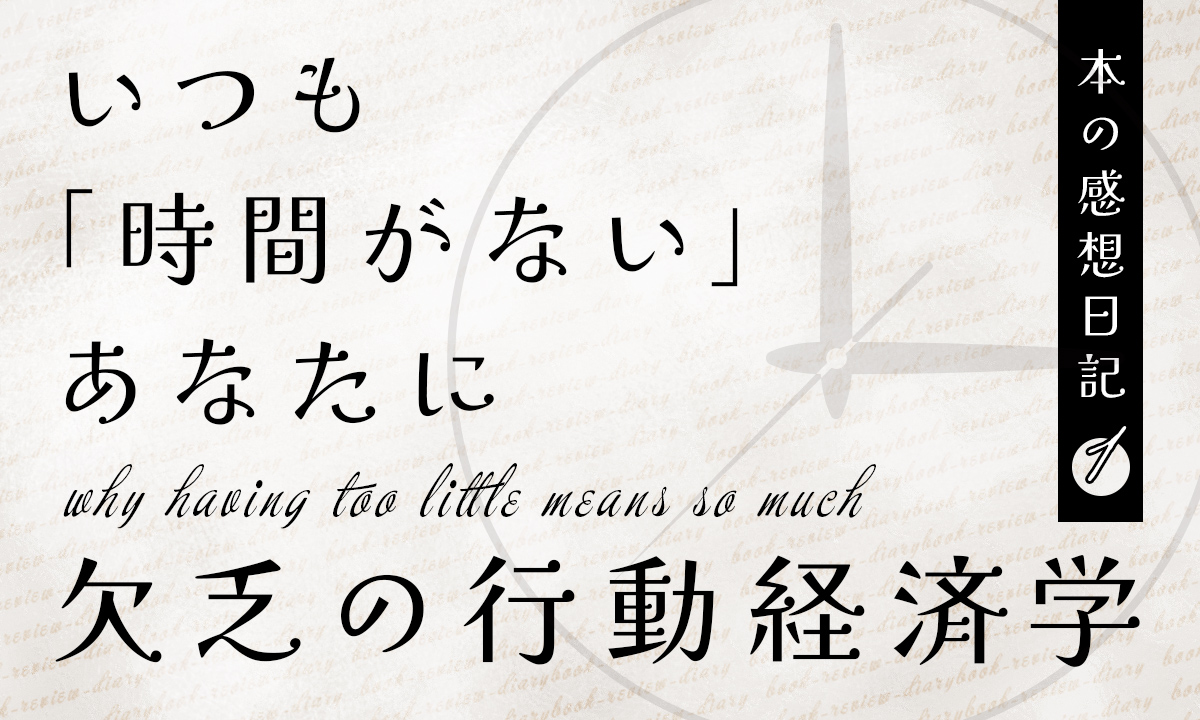
というのも、本を読んでも本質や気付いた点などをまとめておかないと、記憶に残らなくってすぐ忘れちゃうんですよね…。せっかくブログを書いているので、備忘録感覚で記事にしていくことにしました。
完全に個人の独断と偏見の混じった感想文にはなっていくと思いますが、読んだことないって方の参考になれば幸いです。
目次
あらすじ
リンク
なぜ欠乏に陥ると時間が無くなるのか?という問題を豊富な事例とともに解説した本です。
まずこの本の序章には「私たちがこの本を書いたのは、忙しくて書かないわけにはいかなかったからだ」という趣旨の文が載っています。
物語の流れとしては、多忙で時間のない生活に悩みを抱えていた著者たちが「アメリカの低所得者の生活に関する本」への寄稿の機会を経たことをきっかけに、時間の欠乏がもたらす行動や心理状況に気づくことになります。
それを検証するため実験、研究を重ね、わかった事実を事例ごとに淡々と紹介していってくれる…そのような構成になっています。
印象に残った点
- 人は欠乏すると処理能力が著しく低下し、未来の予測など複雑な思考ができなくなる。
- 欠乏していると、欠乏している物に対する注意力が鋭くなるが、代わりに他のことに対する注意力が著しく下がる可能性がある。
- 選択するという行動は脳に負荷がかかる。しかし余裕があれば、その余裕から時間やお金を切り出して選択しないという決断を取ることでそのリスクを回避できる。
- 人が欠乏に陥るのは「個人の資質」ではなく「環境」による要因が大きい。
結論として、何らかの欠乏を感じ続けていると人は処理能力が落ちていき、正常な判断を下せなくなるため、常に余裕を持ち行動することが大事というような話でした。
「集中ボーナス」「トンネリング」について
本の中で語られていた「集中ボーナス」「トンネリング」という概念には身に覚えがあり考えさせられました。
- 「集中ボーナス」…締め切り間際になると全集中して一時的に能力が高まり、短期間で物事を終わらせられる。
- 「トンネリング」…集中するべきこと以外に意識が回らなくなり、ほかの大事なものを見落としたり忘れたりする。
例えるならば…
「締め切りが三日しかないのに必死で原稿をして完成させた。しかし印刷所への振り込みのことを忘れていたのでイベントで結局本を出せなかった…」
- 「原稿の完成」=集中ボーナスによるメリット
- 「印刷所への振り込み忘れ」=トンネリングによるデメリット
…というような形で相関しているわけですね。
自制心の話
自制心はすり減るもの、という話も興味深かったです。
作中で例に上がっていたのはダイエットの話でした。
食べたいものを我慢していると逆にそればかり食べたくなってしまう…という心理状況の話にはうんうんと思わず首を縦に振ってしまう説得力がありました。
やみくもに我慢を続けても逆効果なので、たまに自分にご褒美を与えたり、休憩期間を挟むなりするのが効果的とのこと。自制をする中でも余裕を持つことの大切さが説かれていました。
選択の間違いは常に余裕があるときに起こっている
選択の間違いは常に余裕があるときに起こっている、という話は耳に痛かったですね。
余裕があるから後回しにして、結局すべての締め切りが後ろ倒しになっていく…。
身に覚えがありすぎて頭を抱えたくなりました。
欠乏に陥るのは個人の資質ではなく、環境が大きい
この本の中では、主題として時間の欠乏と金銭の欠乏の相関性について詳しく説かれています。
その中で、そもそも欠乏に陥る原因が「個人」にあるのか「環境」にあるのか、という点を実験によって検証しています。
その理由としては…
- 欠乏に陥る原因は誰にでもあり、その原因を克服できるかどうかはその際に欠乏を埋めることのできる「時間・経済的余裕」などがあるかどうかが大きく関わっている。
- それは生まれだったり、問題が起こった際の経済状況などに左右されるため、補填できる「余裕」がない状態ではだれでも欠乏に陥る可能性がある。
上記のような理由が挙げられていました。実験結果を用いて丁寧に説明されているので、個人的には内容にも納得できました。
特に能力の低い人のパフォーマンスが低いのは、そもそも欠乏によって能力が低くなっている可能性を要所要所で解説していて「個人を変えようとする」のではなく「環境をいかに改善するか」の大切さを感じさせてくれる内容になっていたのが印象深かったです。
まとめ
この本では欠乏が起こるプロセスの説明と、人にもたらす悪影響の説明、それに対する警鐘が主な内容として載っています。具体的事例が豊富で、日々の生活が忙しいと感じている人ほど刺さる内容が多い、自分の生活を見直すきっかけになってくれるような本だと感じました。
しかし、欠乏を解決するため日常で試せる具体的ノウハウ…のような実践内容はあまり記載されていません。ハウツーなどを期待して買う本ではないので、その点は注意です。
本の中で様々な欠乏に関する事例が紹介されていますが、一度欠乏を経験すると負のループから抜け出せなくなる。余裕のあるうちに対処しておけ、日々の中で余裕を作る努力をするべき、という警鐘がどの事例にも含まれていた印象です。
だからこそ、すでに貧困などで欠乏に苛まれ、余裕をなくしてしまった人を救うのはとても大変なことなのだというのが、本を読んでいて痛いほど伝わってきたので、そこは少しやるせなかったですね…。
ないものを補うことは中々に難しいことですが、そこに意識を集中しすぎないでやるべきことをやって余裕を作っていくことが大事なんだな、と再認識させてくれた本でした。
効率的、を追求しすぎると、無駄がない=余裕もないという状況に陥ってしまう場合もあるんですよね。
例えば…
冷蔵庫のものは毎日使い切り、買い物に毎日行って必要な分だけ食品を買う習慣があった場合。
これは無駄なものを買って無駄な出費をするリスクを抑えたり、食品ロスを少なくできる効果があるという点では効率的で良い習慣に思えます。
しかし、毎日健康で買い物に行く時間が取れれば問題ありませんが、何らかの理由で買い物に行けない日があったら?
大体はそういう時に備えて非常食などをストックしておくかもしれません。
とはいえ、そういった先のことを考えておくキャパシティがなかったり、ストックを補充するのを忘れていたりしたら?
そのうえ病気で寝込んでしまっており、外に食べにもいけない状況だったら?
そうしたら空腹でその日は過ごさなくてはいけないかもしれません。
これは工場の在庫などでも同じことが言えます。
在庫の管理に費用が掛かるからと在庫数を減らし普段の管理費用を浮かせることができたとします。
しかし急な問題が起きて、普段在庫など出さずとも毎日の生産品で賄っている部品が供給できなくなり急遽在庫が必要になったとき。その数が足りなかった場合どうなるのか?
ないものはないので、出せずクライアントに迷惑をかける、出荷が遅れるというデメリットが生じます。
もしくは埋め合わせのため、多額の費用を出して他メーカーの在庫を当たって何とかするという場合もあるかもしれません。
その際に失う費用や信頼は、普段の管理費用を浮かせた分の効果と見合っているのか。
それは難しい問題になるのではないでしょうか。
もちろん費用を浮かせる過程でそういったリスクと損失に対する検証や対策を行ったうえで、そういった施策を行っている企業等がほとんどだとは思いますので、これはあくまで「もしかしたら」の話にすぎません。
問題が起こる心配ばかりして無駄を削らないというのはそれこそ愚策とも言えますよね…。
しかし問題とはいつ起きるかわからないもの。
頻発するリスクでなければ見過ごされる場合も多いのではないかと思ってしまったりもします。
想像できないリスクに対して、何らかの余裕を、キャパシティを常に持っておくことは、やはり大切なことなのかもしれないな…と本を読んでいて感じました。
効率的な生活を目指せば目指すほど、こういったある種の無駄や余裕といったものがもたらしてくれる恩恵を忘れていってしまっている気がします。
もちろん、だらだら過ごしていたら時間も余裕もどんどん減っていくし、できることもできないまま…。
とはいえ、時には一歩立ち止まって自分の生活を見直して、何が無駄で、何が必要なのか。
その無駄は本当に不必要なのか、効率的だと思っていたものがどれだけ余裕を削っているか。
そういったことを意識する時間が、余裕があるという幸せを感じられる瞬間があるということが、日々の中でもっと必要なのかも。
と、この本を読んでいて思いました。
気になった方は是非一度読んでみてください。
時間管理に悩んでいる方などは、考え方を見直すきっかけとしておすすめです。
Adivleでも配信されていますので、読む時間がないという方は耳で聞いてみるのも良いと思います。
かくゆう私もオーディブルで聞きました。通勤、通学時間や作業しながらインプットできるところが嬉しい!
なんか身に染みる内容が結構多くて、なんでも後回しにせず余裕を持つのって大事だよなぁとしみじみ感じました。
サボらず計画通りやるのが一番!!
でも人(というか自分)はすぐ怠惰に逃げる生き物…うーん世は無常…なんとかなれー!